第22回別冊スクラップブック『二枚のデッサン』
予定日は12月2日で、生まれたのは14日。われながらのんびりしていたと思う。いや、出てくることに対し最後までしりごみしていたのではないだろうか。その逡巡は妊娠三ヶ月目に切迫流産しかけたという話からもうかがえる。突如、出血し、何人ものお産を見てきたぼくの曾祖母(明治生まれ)でさえ、あわてて医者に行くよう世話した。
検診から分娩までを手がけていたのは、白澤實先生だった。先生は地元で長く産婦人科を営んでいたが、こればかりは痛み止め等を施す以外には処置しようがなく、この一日が峠で、あとはこの子の生命力にかかっていると言った。次の日、心音が聞こえた。意志の力、先生はそう表現したらしい。でももし意志があったとしたら、ぼくはただの優柔不断で、そのためらいが迷惑をかけたとみる。
この「出るか出まいか」の戦いは、ええいと鉗子で頭を引っ張られてもすぐに勝負はつかず、ぼくは、二十秒間泣かなかった。母はいつまでも泣き声がしないので相当焦ったようだ。この世が怖かったのか、それともよほど意固地だったのか。しかしそれもつかの間、白澤先生の手のなかで、ぼくは思いっきり泣くことができた。その表情を知っているのは、先生しかいない。
果たして「出た」のが正解だったのか、今でも思い悩むときがある。なんていうと、またまた周囲を困らせてしまうが、「人生はままならない」ことを思い知るのも、成長してきた証なのだと受け止めている。激しく動けばそれだけ摩擦が生じる。泣くのが悲しみではなく生き始めたことのしるしであったように、身を焦がす熱は生き続けていることのあらわれだ。生命は太陽のように無条件に燃え、人はこの手に余る神秘的な力を、人生という火かき棒で四苦八苦しながら自分のぬくもりに調整していく。
思春期、反抗期、低迷期。自らの熱にやられて火傷をすると、なにもかもがいやになる。そういうときの助言は耳に入らない。あのときもそうで、父が「白澤先生の息子さんが本を出しているぞ」と言っても「テレビに出てるぞ」と言っても、勘弁、勘弁とふさいでいた。実を結ぶかわからない努力。必死にもがいていた。
それでいながら、ふと思い出すのである。二十秒後に呼吸を理解したように、遅ればせながら。すっと父の本に手を伸ばし、書店のブックカバーを外す。――白澤卓二。順天堂大学教授(医学博士・加齢制御講座)。日本抗加齢医学会理事。
抗加齢(アンチエイジング)は自分には程遠い世界に感じられた。むしろ夭逝のロックスターに心酔していたから、長生きしたってしゃあない、太く短く生きようぜと粋がっていた。
ところが、気づけばエディ・コクラン(21)、バディ・ホリー(22)、オーティス・レディング(26)、尾崎豊(26)の没年を越え、数え年でジミ・ヘンドリックス(27)、ジム・モリソン(27)、ジャニス・ジョプリン(27)、ブライアン・ジョーンズ(27)の有名なゾーンに踏み入れている自分。レジェンドになる気配はまったくなく、このままではただのアラサーになってしまう。
そして、たぶん、なる。“ままならない”とは“生きざるを得ない”ということに他ならない。そう簡単に「太陽」が尽きるものであれば、世に哲学など生まれはしなかっただろう。死ぬまでの、案外長い道のり。「太陽」は目をそむけたくてもその生き様を照らし出す。命の力は意志よりも強い。
父の紹介から数年、ぼくは白澤卓二さんの書かれた『老いの哲学』を手に取っていた。「太く短く」は夢と消え、親の背中をのこのこと追う。父の買ったその本にはしおりが挟まれており、おのずとそこからページが開かれた。
“私の父親は群馬県で産婦人科医院をいとなむ医師でした。父は地域医療のなかで品を持ちながら、5000人以上の誕生に携わり、その生命が健やかに育つ姿を見守ることを最大の使命とし、そして美徳と考えてきました。”
この「白沢医院」でぼくは生まれた。
“お母さんと赤ちゃんが退院するときに、父親は病室に色紙2枚と絵筆を持っていき、赤ちゃんのデッサンを2枚描きました。1枚はお母さんに渡し、もう1枚はアトリエに保管しました。”
ある冬晴れの日、仕事を終えたぼくの足は、群馬県館林市に向かっていた。無性に「ぼく」と会いたくなった。医師にして画家の残した絵が、実家のどこかに眠っている。家族ともども東京に引っ越しているので、そこに住んでいる者はいない。駅でタクシーを拾い、行き先を告げる。
「今日は暖かいねえ。昨日まで風がすごかったんですよ。」
「からっ風ですね。」
「こちらの人で?」
「ええ。帰省……かな。迎えがなくて。」
目印となるアパートの名前を伝えた。
「まだありますか。」
「わからないな。あの県道の細い道入ったところでしょ。」
「そうです、よくご存知ですね。」
「あそこに住んでるの?」
「いや、あの近くに住んでいました。」
――高校を卒業するまで。ささやかな庭があった。父の部屋と繋がった自室があった。子供の頃は顔を出せば父が見られて嬉しかった。でもだんだんと、この設計がうっとうしくなり、二つの部屋のあいだにある引き戸は一条の光も入らないくらいにピシッと閉めていた。思い出もそんなふうに見えなくなっていって、目を開けたときには父が「父」となった年齢になっていた。
その扉を開けると父がいる気がした。階下から母の声が聞こえて、一緒に降りる。家具がずいぶんと小さく見えて、ドールハウスみたいに愛おしく、でもそれは、途中で切り上げられたママゴトのように寂しく映った。
「あの、白沢医院の白澤實先生って知ってますか?」
「知ってるよ。」
あっけなく答えられた。
「絵も描かれていたんですよね。赤ちゃんの。」
「それだけじゃないよ。美術館だってあるし、市役所にも飾ってある。」
「そこで生まれたんですか。」
「いやいや。運転手やってればね。」
ぼくの「絵画」探しが始まった。勝手に来たから在りかはわからない。「描いてもらった」「まだ家にあるはず」、前に聞いたその言葉だけを頼りに鍵を回した。意外にきれいに片付いている。父が定期的に風を通しに帰っているのだ。
“かつてここに三人の家族が暮らしていましたが、みんなそれぞれに歳をとりました。この家も、この町も。ただ風を通しに、この写真の男の人は訪れます。電気も水道もガスも止まっていますが。電話はもちろん通じません。あの番号はなくなりました。その番号を写真の子供は今でもそらで言えます。家に帰るとき、なんども押したからです。電話にはいつもこの女の人が出ました。少年がかければ、少年がかければ、また出てくれるでしょう。でも少年は足早に駆け去り、誰も帰れなくなったのが、この家です。”
何十冊と積まれたアルバムがこの家の住人だ。呼び出して、一枚、一枚に語りかける。平成から昭和に遡るにつれ、人々はやたら多くなり、一時の活気をとり戻す。しかしある時点で、一人の少年が姿を消す。――昭和63年。
(アルバムより:原文ママ)
S 63. 5か6月
「のり 同りょうだった友だちの結婚式に招待され、私もついていってしまう。」
S 63. 秋
「安定期で 体調も良く 一番ゆったりしていた頃。」
S 63.12.12
「のり 仕事早退して 私の入院につき添ってくれる。病室に入ってすぐ 身の回りの整とんしてくれる。」
次のページでは、ベッドに腰掛けた女性がピースサイン。
「私 これから始まる出産の前に まだ余ゆうのピース!!」
「ヒエーッ!! 私のこの むくんだ顔・姿! 体重なんと12.5kg増。(ふくらはぎ押すとそのままで戻ってこない状態…。)」
「陣痛が始まり 痛みだしてきたので こらえている所…。」
「12.14 午前3時すぎだと思う。(出産後30分以上)やっと出産して、病室に戻ってきて、パパがすぐとってくれる。(パパは家からすぐとんできてくれた。)」
「産み終わると この笑顔。笑顔。 なぜか二人 手にぎり合ってしまった!」
横たわる母の手を、スーツ姿の父がにぎる。――いつしか呼び名も変わっていて。
「私の目線は……もちろん 我子「悠介」にいっています。心配そうなこの目つき。」
――まだかぎ括弧でくくられた名前。
「白沢先生が プレゼントに描いてくれた 「悠介」の生後1週間の顔。とっても似ています。」
この絵だ。だがぼやけている。どんな顔して、しがみついて、出てきた?
写真は家中にあるくせに、肝心の絵、一枚が見つからない。いま電話したらわかるかもしれないが、自分の力で「自分」と出会いたかった。迷いもある。すでに紛失しているかもしれないし、この場にあるとは限らない。それでも「自分」は失くしてないし、今でもそれはここにあると信じている。
立派な額縁や写真たての中身まで調べた。重ねて入っている可能性もあるからだ。しかし発見できずに日は暮れて、電気のない部屋は薄暗がりになっていく。腰に手をあて、物置と化したクローゼットに目を凝らす。「色」が垣間見え、ファイルを引き抜いた。それは幼少期からのお絵かきを溜めた“画集”だった。顔から手や足が伸びていたり、色使いが現実のそれとはかけ離れたりしている代物だ。子供はおしなべてそんなものだが、自分のは度を越して下手で目を疑う。ただ“生まれる前の従妹”と称しそれが円形に描いてあるのには笑った。
笑みを浮かべたまま「自分」と出会った。気持ちよさそうに目をつむっている。苦しくない、安らかな顔。心のまま好きに描いた絵に挟まれて、白澤先生のデッサンが保管されていた。両手で取り上げて、じっと見つめて感じとる。先生も、悦びに満ちあふれて筆を執っていたに違いない。そしてそのまなざしのなかで、何千人もの赤ちゃんが祝福を受けてきた。無条件な生命をそのままに走らせる絵筆によって。
白澤先生の最期はがんとの闘いだったという。
“(平成23年に)医院を閉じると、間もなく入院。病室では、これまでに描いてきた絵を眺めて、人生の最期を自分らしく終えるために静かな時間を過ごしていました。そして、6月13日の未明、情熱を持って描き続けてきた絵のかたわらで父・白沢實は亡くなりました。享年85歳。” 白澤卓二『老いの哲学』
その手は教えてくれた。この世に生を受けるとは、単に“生きる”でも、ままならずに“生きざるを得ない”でもなく、まずもって“生かされている”ことなのだと。出会いの瞬間に抱きしめてくれた人が描きとめる、元来の、柔らかな生の感触。たとえ自分がそれを忘れそうになっても、分かち合ったもう一枚の絵が、ぼくを忘れない。あの日たしかにぼくは泣き、その後、こんな表情で生を享受し始めた。ゆっくりと生まれてきたのだから、自分らしく、ゆっくりと歳を重ねていこう。
――産み終わると 笑顔
なぜか二人 手にぎり合ってしまった!
白澤實先生に捧ぐ

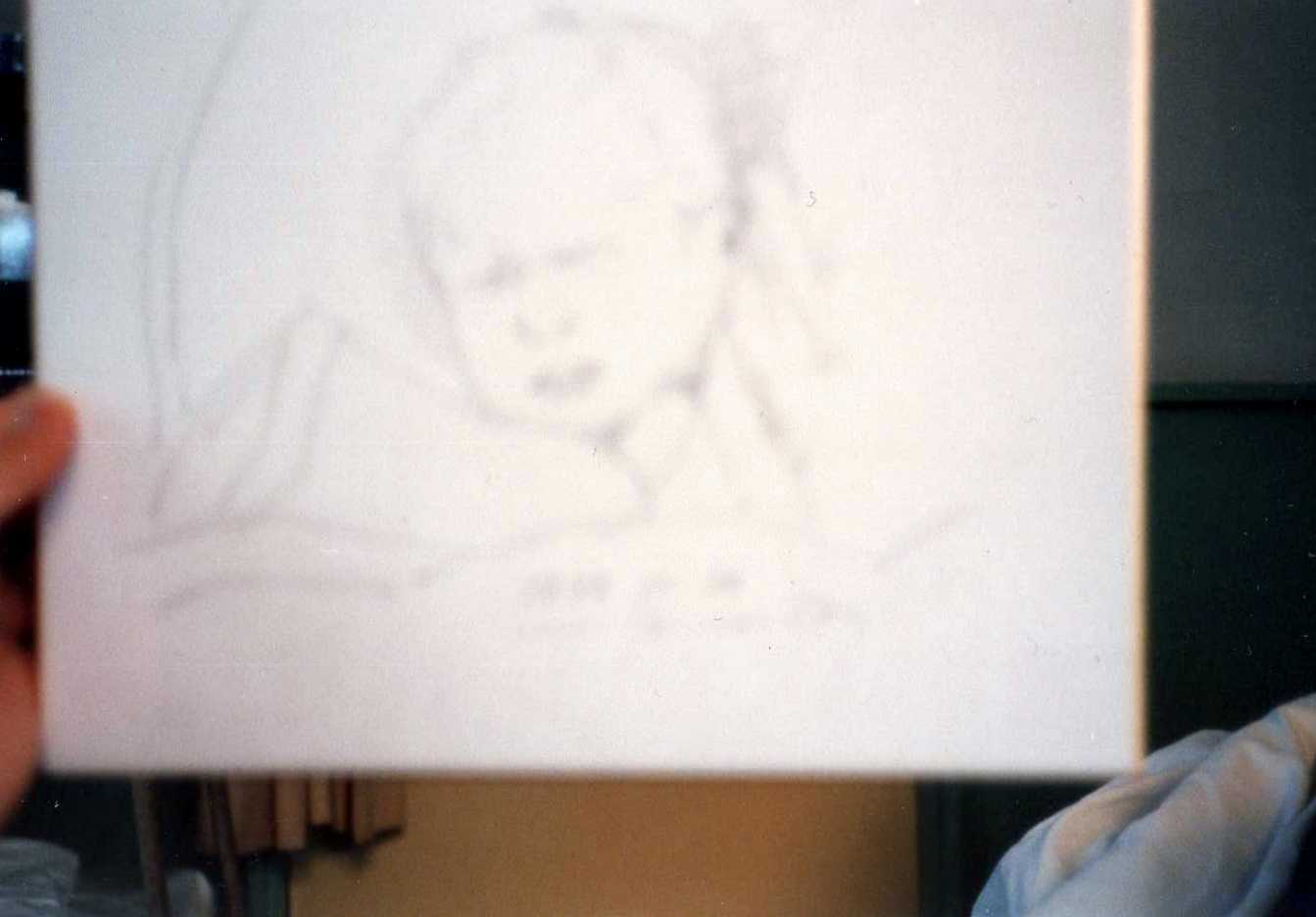


コメントを残す