『祖父の十五年戦争 / 満州入植からシベリア抑留へ』
以下の記録は、祖父の沈黙からこぼれおちた言葉と周囲の証言、そして史実をもとに構成された戦争体験、ならびにある一族の約百年にわたる歴史である。その作業はかけらを見つけては想像し型にはめ合わすジグゾーパズルのようであり、絵画修復にも似ている。いずれにしても浮かび上がった全体像が正確かどうかは祖父当人しか知りえない。また関係者への配慮から若干の脚色も加えている。しかしこの歴史を貫く本質は変わらないよう細心の注意を払って書かれている。
その晩帰宅すると父はすでに寝床に入っていた。老境というにはまだまだ早いが五十も過ぎると体力の衰えが傍から見てもよくわかる。かつて息子を肩に乗せて歩いた背中もだいぶ小さくなった。丸まった寝姿はさらに小さい。そっと荷物を降ろし、部屋の明かりをつけると、枕元に置かれた一冊のアルバムが目に入った。静かに引き寄せ、一枚、一枚めくっていく。どの写真も「昭和六十一年」のもので、若き日の父と母が、今は亡き父の両親とともに写っている。
そこは長野県の田舎町。祖父の家には母屋と離れがあり、その裏に畑があった。採れたてのトマトを水で軽く洗い流して丸かじりしたあの美味しさをよく覚えている。ぼくは祖父の薄い頭に吸盤をくっつけては笑っていた。「いてえだよ、いてえだよ」と声を出す祖父にもっと笑った。「鉄かぶとのせいでこんなに禿げちまっただよ。」
夏でも涼しい風が網戸を通して入ってくる。祖父は夜になるといたずら坊主を膝の上に置き、戦争の話をゆっくりと語りはじめる。「ユウスケや、ユウスケや……」しかしそのほとんどは思い出から抜け落ちている。父から聞くに祖父は通信兵だったようで、日中戦争から徴兵され、最後はシベリアに抑留され帰ってきた。だが具体的になにがあったのかは口を閉ざし続けた。足の踵近くには鉄砲玉を受けた痕がある。ぼくはただ祖父の “ツートントン、ツートントン”と信号を送る声が耳に残っており、その響きが好きで途中で眠ってしまう……。
1919年(大正八年)マツスケ
祖父マツスケは、大正八年、八人兄妹の次男として生まれる。長野県の山深きところ、彼らはそこを「シガの家」と呼んだ。長男は早いうちに帝都・東京へ出ており、あとは女姉妹ばかりだった。祖父は小学校を卒業して間もない「十七歳」で日中戦争へかり出される……。ここで疑問に思うのは、日中戦争の開始(1937年)にあたって、未成年男子への徴兵があったのかということだ。調べていくと、関東軍が与する「満蒙開拓青少年義勇軍」という計画があった。これは十五歳から十九歳までの青少年を対象にし、満州で開拓に従事させながら軍事訓練を受けさせ、抗日ゲリラの襲撃に備える「武装開拓団」を募るものである。1936年、広田弘毅内閣は二十年間で五百万人を入植させる政策を打ち出していた。祖父の“徴兵”年齢と一致している。
「関東軍」の創設は大正八年、日露戦争で満州を勢力下に収めた権益を守るべく、中国関東州と満州に駐屯した日本陸軍の総称で、祖父と“同い年”のこの組織が、彼の人生を翻弄していくことになる。
さらにわかったのは、この関東軍の「義勇軍」に青少年を送出した県のトップが、長野県なのだ。その理由は「信濃教育会」がお国のためと率先して若者を導いたためとされる。長野県からは6939人が送出されて、1360人が帰らぬ人となった。犠牲者の割合は20%にもなる。
家族の長男はいない、他は女性、そして「義勇軍」に熱を上げる長野県にいるとなれば、出されるのは祖父と考えられるだろう。おそらく「信濃教育会」の積極的な勧めで(満州国は内地より安全だ、満州開拓は豊かな生活をもたらす等々)祖父は半ば強制的に参加することになった。
つまり祖父は「開拓団」として中国の北へ行こうとしていたのだ。もし日本が戦争に勝っていたら、祖国には戻れず「満州国民」になっていたはず……。
「義勇軍」に入った者はまず茨城県の内原訓練所に送られる。そこで一定期間の訓練を終えると満州に移送、開拓地へ入植させられた。スローガンは「右手に鍬、左手に銃」。――祖父の“十五年戦争”がはじまった。父親は、息子が異国へ旅立ったのを見届け、亡くなった。
祖父は“二度徴兵された”と語り継がれている。一度目の“徴兵”は十七歳の「満州入植」であった。祖父は寒さと粗食に耐え忍び、軍事訓練と原野開拓、そして農作業に勤しんだ。その間、日中戦争は長引き、太平洋戦争が開戦、日本は第二次世界大戦の戦渦に巻き込まれてゆく。敗戦の気配は遠く北満州まで覆っていたが、南方に出向いた兵士たちとは違い、日ソ中立条約により祖父のいる満ソ国境地帯が前線と化すことはなかった。しかし1945年の夏、関東軍は十八歳から四十五歳までの在満邦人男子約二十万人を招集すると発表。このいわゆる「根こそぎ動員」によって祖父は再び“徴兵”されたのである。二十六歳の時だった。
関東軍の師団に属したものの人員は少なく、兵装も貧弱だった。鉄帽だけは行き届いた。新京(満州国の首都)の召集令状にはこう記されていた。「各自、かならず武器となる出刃包丁類およびビール瓶二本を携行すべし」。
同年八月九日、ソ連は中立条約を破り対日参戦に出る。“出刃包丁”など一笑に付す圧倒的な戦力で満州になだれ込む。国境付近の関東軍は次々と消息を絶っていった。というのも、兵力の問題以前に、軍隊を指揮する上で必要不可欠の通信網さえ構築されず――祖父の任務はこの「通信」だったわけだが――師団間の連絡がまったくとれない状況にあったからだ。役に立たぬ無線を持った祖父は後退に後退を重ねる。多くの仲間たちが――入植者たちが――砲弾でやられていくのを尻目に。(おらあ、ここで死ぬだ。次はおらだ。次は……)ついにソ連兵に囲まれた。部隊は崩壊、逃げ惑う兵士たちを大挙して押し寄せるソ連兵が狙い撃つ。手榴弾も飛び交い破片が身体に突き刺さる。(いてえだ、いてえ、死にたくねえだ、こんなとこで死にたくねえだ。)祖父は倒れた。銃弾が足を貫いた。(なんのために開拓してきただ……故郷を捨てて……)
ソ連侵攻が伝わり、関東軍は満州鉄道と協議し「避難列車」を出すことにした。当時、新京の日本人は約十四万人いた。“民間人を最優先”にという原則は建前で、実際に列車に乗れたのは関東軍の軍人やその家族がほとんどだった。総司令部の家族のなかには、特別機で日本に帰った者もいる。民間人は、来ることのない列車をひたすら待ち続けた。
満州での戦いは八月十五日を過ぎても続く。「玉音放送」など届かぬ地。しかしながら天皇は勅語で関東軍に降伏の許可、「降伏しても“辱めを受ける”捕虜ではない」との伝達をしていた。それでもなお関東軍は抵抗し、通信を随所で分断する。
停戦協定が成立したのは、八月十九日。満州開拓民にとって八月九日からのこの十日間が最初の生死の境目となった。八月二十二日、関東軍は「満州国」の新京にあった総司令部本庁舎をソ連軍司令部に引き渡し、満州は、日本の手から離れた。
捕虜となっていた祖父は武装解除を命じられた。ソ連兵に導かれ、生き残った者たちのもとへ集められた。ソ連兵はなにやら「ダモイ、ダモイ」と口にしている。しばらくその場にとどまるよう指示された。足が痛んだが誰もが怪我人ばかりでなにも言えない。(戦いは終わっただ。これでけえれるだ。でも満州に戻るよりも、日本がいい……。)列車がやって来た。ソ連兵は「ダモイ」を繰り返す。わけのわからぬまま同胞と乗り込む。帰れる、帰れる、と口々に言い合う。祖父は疲れきった顔で、十代から開墾してきた土地を振り返った。
列車はそんな追憶を無視するかのように北へ北へと進んでいった。祖父は約十万人の「満蒙開拓青少年義勇軍」の一人から、約六十万人の「シベリア抑留者」の一人へとなっていた。
俗に言う「シベリア抑留」は、ソ連による日本人捕虜のソ連領土内での強制労働を指すが、場所は“シベリア”に限らず、東はカムチャッカ、ベーリング海に面する東経160度から、西はモスクワ近郊、ドニエプル川流域の東経40度に至り、北は北極海に近い北緯70度から中央アジアを経てパミール高原の西麓、北緯40度までの広大な地域に及ぶ。よって実態は「ユーラシア抑留」であり、祖父は満州からユーラシアのどこかの収容所に送られた。その数は二千ヶ所とされ、場所は特定できない。祖父が決して語らなかったことの一つだ。ただこう言い残している。“便は凍ってしまうので手でかき出した”と。
便が凍る、とは零下三十度から四十度あたりの環境で労働させられた抑留者の手記によく見られる。穴を掘ってその上に木を二本渡す。これがトイレだ。そこで足された糞尿は凍り、氷柱となる。当番はそれを棒などで突き崩す。氷の破片が服につくと、トーチカで溶けて臭気を放つ。
祖父の収容所はここから想像するに高緯度の“シベリア”にあったと考えていいだろう。収容所によって様々な労働がノルマとして与えられた。「飢え」と「極寒」と「重労働」がシベリアの収容所には共通している。祖父が帰国したときの姿は、お腹だけが膨らみ、あとは骨と皮の典型的な栄養失調の状態だった。死者は1945年から46年に集中し、その二年で四万人強が亡くなっている。死因はほぼ病気と栄養失調だった。シベリアでは病むことは死ぬことを意味していた。(明日はわが身、明日はわが身だ……)祖父の眼にしてきた死者の数は計り知れない。凍土を火に当て溶かし、穴を掘って埋めた。今も凍てついた大地の下に眠る戦友がいる。彼らの命の上に祖父は立っていた。その息子、その孫も……。
(この戦争はいつ終わるんだべ……。なあ、おらはただの百姓の息子だっただよ。それが、それが……)祖父の口をつぐませたのは夥しい死者だけでなく、収容所内ではじまった「赤化運動」だったと思われる。やがて日本人捕虜には徹底した“思想教育”がなされるようになった。そのために創刊されたのが「日本新聞」で、ソ連人を編集長とし、日本人スタッフも混ざって執筆された。内容はその名に反し、共産主義の礼賛、反米・反資本主義的な視点からの国際情勢、日本の天皇制打倒の呼びかけなどであった。要するにソ連の「宣伝新聞」だ。この赤化運動の担い手は「アクチブ」と呼ばれ、日本人の“反動的態度”を発見したら、大勢の前で「吊し上げ」を行なった。捕虜が捕虜をリンチし辱めるのだ。しかし「ダモイ」のため、抑留者たちは表向きはソ連とスターリンを称賛し、対象となった捕虜を攻撃した。さもなければ、自分が吊し上げられる……。(おらこんなことしたくねえだ、おかしいだよ、“解放者”がおらたちをずっと抑留してるだに、でもそんなこと言ったらダモイが……)
ダモイ、それは帰国をあらわす言葉。ダモイを告げられた者は引き揚げ船の出るナホトカに集められる。しかしそこで待つアクチブに「反動」の烙印を押されたら帰国は取り消される、そう信じられていた。「帰国後は代々木に集ろう」が合言葉だった。代々木には日本共産党の本部があるからだ。ナホトカでは「資本主義、粉砕!」と叫ぶことが賢明な姿勢だった。
抑留者の引き揚げ時期は、「1946年から50年」の前期、「53年から56年」の後期に大別される。1946年、米ソの間では日本人捕虜を毎月五万人送還するという協定が締結されたのにもかかわらず、その通り履行されなかった。加えてソ連はGHQに48年四月まで「領海が凍結する」との理由で引き揚げを中止すると通告している。祖父の引き揚げ時期もまた語られていないが、後期まで残された抑留者が、ソ連の声明通り“戦争犯罪人”であるとするなら、前期に引き揚げた可能性が高い。そして“凍結による中止”から再開した時期で、かつ「シベリア帰りはアカ」というレッテルが貼られるようになった48年か49年に帰っているのではと推測する。引き揚げ後の、戦争についての頑な沈黙、警戒ともとれる寡黙さを考えると、周りに「赤い帰還者」ではないことを訴えているようにみえる。実際にシベリア帰りだというだけで警察につきまとわれた者もいる。住民が温かく出迎えてくれると期待していたら“アカが来た”と差別された者もいる。シベリア帰還者への市民の目は、時代が時代だけに厳しかった。逆に日本政府はソ連の実情を知りたがり帰還者たちから情報を得ようとしたが、彼らの多くは担当官の質問に対して「忘れた」「わからない」あるいは“沈黙”を守ったという。
1949年、ナホトカから祖父を乗せた船は京都の舞鶴港に入港した。タラップを降りる。辺りは騒然としている。赤旗めがけて走る者、それを引き止めようとする親族、興味本位で帰還者を眺める大衆。祖父にはなにもかもが遠い世界のことのように映る。自分のなかでなにかが失われている。(おらは、帰ってきただよ、もうよくわかんねえが、帰ってきただよ……月の沙漠を歩いてきただよ。)十七歳の少年は三十歳になっていた。
1962年(昭和三十七年)ノリヒコ
父ちゃんは怖い。なんでもいいだ、いいだで済ませる。食えればいいだ、着れればいいだ。あとはむっつりと押し黙っている。おれは「シガの村」を四歳で出て、新しい家に来た。父ちゃんと母ちゃんがそれぞれ郵便局に勤めて貯めたお金で「オモヤ」を買った。でもあんまりいい思い出はねえ。大好きだった戦車のプラモデル、父ちゃんなにも言わずに全部放り投げちまった。あのときは鬼のようだった。なんでそんなことする。とにかく早く大人になりたかった。大学入ったら逃げるように都会に出て一人暮らしはじめた。心底ほっとした。ただ、その金を出してくれたのは父ちゃんだ。“これからは大学は出なきゃいけねえだ”と言い張って。大学出たってどうなるかわからねえけど、とにかくミツコと出会えた。今日、ミツコは父ちゃんとうまく話せるか、不安でしょうがない。
ミツコは少し緊張しているけど、列車で嬉しそうにアイスクリームなんか食べたりして、なんだか楽しそうだ。さあ「オモヤ」に着いたぞ。ありゃ、父ちゃんいきなり「おら群馬なんて知ねえだ」はねえよ。隣の県だべ。ミツコ困ってるで。ああ、母ちゃんがフォローしてくれた。「ノリをよろしく」って、なんだか恥ずかしいけどな。いくつかって? 同い年の三十七年生まれ。今年で二十四歳だ。
1988年(昭和六十三年)ユウスケ
昭和六十一年というと、ぼくが生まれる二年前か。父さんも母さんも若いなあ。軒先で花火をしてはしゃいでる。ぼくも祖父の家の同じ場所で花火をした。でもこの写真の祖父はぼくの知ってる「じいちゃん」じゃない。
がっしりとした体躯、その目はとても鋭くて、瞳を見つめると、戦争の影が揺らいでいるようだ。父さんはじいちゃんは無駄なことは一切しゃべらなかったって言うけど、確かにそんなオーラが出ている。……だけど父さんも無口なほうじゃなかったか。ただ空手ばかりに励んで言葉の前に相手を張り倒す。ぼくも一度ぐずっていたらベッドの上に投げ飛ばされたよ。顔つきは修行僧のように険しく、肉体はボディビルダーと見違えるほど。あの頃、若い父さんは勤務地、郵政省がある東京に単身赴任していて、母さんとぼくは群馬の家で二人きりだった。母さんはぶっきらぼうの父さんのどこに惹かれて結婚したのだろう……。
祖父は当然、うちの母が「オモヤ」に嫁いでくるものだと思っていた。しかし結局は“知らない群馬”に長男を出すことを認める。それには時代の変化もあったのだろう。昭和はもう六十年を過ぎ、過去の慣わしもあの戦争の記憶さえも廃れていった。新しい時代が来ようとしている。帰還後「これからは大学だ」と小卒の祖父が見越したように、次世代の夫婦のかたちもある。また、いち早く東京へ出て戦禍を免れた長男の存在も脳裏をかすめたことだろう。(おらの兄もこの村を出た。田舎は……きっとノリヒコのいる場所でねえ。)祖父は花火に照らされた母の顔を見やる。(この娘は幼稚園の先生だと言うだ。先生なら安心だ。本当はノリヒコも先生にしたかっただ。しかしな、おらの後をついてきちまっただよ。)
昭和六十一年、祖父母に見守られながら、父と母は軽井沢の教会にて挙式。そして長野の地を去り、群馬県館林市に居を構えた。その二年後、長男ユウスケが生まれる。それと入れ替わるかのように祖父の妻、すなわち父の母が亡くなる。昭和という長い長い時代も幕を閉じ、祖父は、自分の一時代が終わりを告げたように感じた。
祖父はユウスケの名にマツスケの「スケ」が入っていることに大変喜んだ。父の代から「スケ」を与えられた者はない。(おらの名を継いでるだ。母ちゃんは死んじまったが、ユウスケが、おらのユウスケが、これから“平成”という時代を生きていくだ。)祖父はユウスケが大学に行けるよう、さっそく学資保険を積み立てはじめた。
ぼくの成長を見ながら祖父はだんだんと柔和になっていった。帰省するたびに「オモヤ」の柱に背丈を刻み、いつも「大きくなっただ、大きくなっただ」と相好をくずした。強面の祖父を見た記憶はない。母に対しても「ミッちゃん、今度の老人会に着ていくかっこいい服を選んでほしいだ」などと接し方が軽くなった。父とは毎回、郵政話に花を咲かせているようだった。そして自分たちの仕事をさかのぼり、孫には「通信」の音を聞かせる祖父。……ツートントン、ツートントン。
ぼくは祖父の運転する車に乗って「シガの家」に向かった。「オモヤ」は田舎だと思っていたが「シガの家」はそれとは比べものにならないほど鄙びた地域にあり、道なき道をがたがたと走っていった。窓を開けるハンドルをクルクルと回すと、これぞ信州という、寒い風が吹き込んでくる。「着いただよ。」
荒野に一軒家がぽつりと建っていた。「ここでおらは生まれただ。父ちゃんも生まれただ。」祖父と孫は家を見上げる。しばらく、見上げている。今ならわかる。この家は十七歳までの祖父を優しく包んだ母胎であり、三十歳の祖父を引き取った乾いた棺桶である。ここには数々の「言葉」が葬られ、沈黙の河の源流となって一族の歴史を貫いた。しかしシベリアにも春が訪れるように、約百年の歳月を経て、「墓前」に立つ者があらわれた……。
祖父の最期は多くの高齢者の例にもれず、認知症になって介護施設のベッドで寝ていた。もう父の顔も名前も忘れていた。ただ宙の一点を見つめてぼうっとしている。でも……ぼくが手を握り目をのぞき込むと「……ユウスケ、や……」と涙を流した。“じいちゃん”が、一瞬だけ戻ってきた。――そうだよ、ユウスケだよ、じいちゃんが寝てる間、いろんなことがあったけど、ちゃんと大学を出たよ、本当にありがとう。ここにいるのは父ちゃんで、いま東京で一緒に暮らしている。そう、じいちゃんのお兄さんが「シガの村」を出て行って生き延びた、あの東京にいるんだよ。
2012年の春に祖父は逝った。ぼくが大学を卒業した春だった。息子と孫を戦地ではなく大学に送り届け、生きているうちに無事に卒業させた。安心したのだろう。それまでは「死にたくねえだ、死にたくねえだ」と世話係の人にはもらしていた。戦友がやって来るとも口にしていた。死ぬのをとても恐れていた。“戦争に行ったのに?” ではなく、行ったからこそ、無残な死を目の当たりにしてきたからこそ、死という存在が、恐ろしかったのだと思う。
だが祖父のあの涙は、長い命を包み込んできた深い河から流れ落ちた雫、再生の光にも見えた。再生、自分の掌を見つめてみる。この手と、戦地をさまよった手とが繋がっている。異国の凍土を歩んだ足が、世代をくだり今、祖国の首都を踏んでいる。祖父の涙はこの血を流れ、一縷の望みとして受け継がれている……。
望み? “ユウスケ”、お前は何者だ? 最期まで祖父の心に刻まれていた自分とは一体誰なのか。祖父は戦争を生き抜いた。父は貧しさを乗り越えた。偶然に偶然を重ね辿りついたその子には、なにが求められている? ……父よ、昭和六十一年のアルバムを見て眠った父よ、ぼくはこの一族の「沈黙」を打ち破ろう。百年の沈黙を。葬られた言葉が一族の末裔の口から蘇ろうとしている。「墓前」に花を手向けるように「言葉」を捧げよう。
満州事変から太平洋戦争の終結までを一般に「十五年戦争」と称するが、ここに見てきた祖父の満州入植からシベリア抑留までの足跡を、「祖父の十五年戦争」と名づけたい。戦争は敗戦で終わらなかった。この命の灯火は、ユーラシア大陸を巡り、飢えと寒さと重労働にも耐え、数え切れない死者たちの代わりに、ここまで託されてきた。ぼくがこの火を使ってまずしたことは、シベリアの凍土を溶かすがごとく、一族の沈黙を――戦争の闇を――照らし掘り起こすことだった。昭和生まれの最後として、平成以降に残すべき言葉を見つけることだった。もうぼくらの子供には伝聞形でしか表現できない。あの“ツートントン、ツートントン”という異国の哀しい響きを再現することは無理だ。この口で言えるのは、「今」は過去からの奇跡的な細い糸で編まれた大切な時間であり、ぼくたちの選択次第で簡単に断ち切れてしまう命綱である、ということだけだ。
祖父から群馬の家に毎年恒例の大量のりんごが送られてきた。いつも食べきれなくてお裾分けにするのだが、そこに一葉の写真が収められていた。父は実家に電話した。
「父ちゃん館林に来てたんかい、これ花山じゃねえか、なんでうちに寄ってかなかった?」
「観光ツアーで行っただよ、抜けられなかっただ。」
「でも来る前に一言くらい……」
「花山のツツジ、きれいだったなあ。あんなの見たことねえだ。世界中探してもねえ。館林……いいところだよ。」
マツスケ
ユウスケ
――末永き平和を誓い、祖父に捧ぐ――
※祖父の足跡を辿り、本稿を書き上げることができた、主な参考文献に謝意を。
栗原俊雄『シベリア抑留――未完の悲劇』、岩波新書、2009年
おざわゆき『凍りの掌』、小池書院、2012年
長野県歴史教育者協議会編『満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会』、大月書店、2000年
※最後に……
マツスケ、二十六歳、ソ連軍と交戦、シベリアに抑留される。(昭和二十五年)
ノリヒコ、二十六歳、ユウスケ誕生す。(昭和六十三年)
ユウスケ、二十六歳、これを記す。(平成二十六年)
絵:さめこ





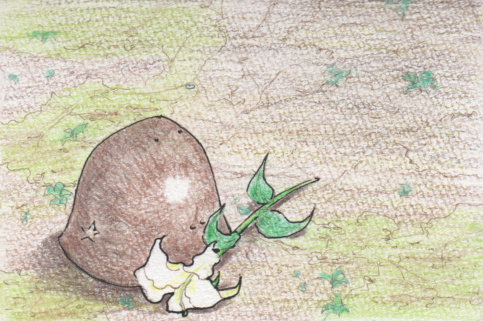
[…] ※関連エッセイ『祖父の十五年戦争 / 満州入植からシベリア抑留へ』 https://shikamimi.com/notes/2518 […]